はこだてわいん×ハコダテアンチョビ
~生産者対談~
地域の生産者が思い描く道南の未来

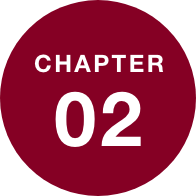 知識も前例もない、
知識も前例もない、
ゼロからの商品開発

- 齊藤さん
- 渡辺さんがおっしゃってくれたように、ハコダテアンチョビはフードロスの問題から始まっているんですよね。函館でマイワシが大量にとれているけど値段がつかないという状況が、すごくもったいないなと思って。もっと上手く回ればいいのにという気持ちをずっと抱えていたんです。
だから、まずは自分のお店でマイワシを使ったメニューを出してみました。でも、なかなかオーダーが入らず、結果的に自店舗内でフードロスが起こるという状態になってしまったんですよね。
―そもそもの話なのですが、函館であまりマイワシが食べられないのは、なぜなのでしょうか?
- 齊藤さん
- もともと函館でとれていた魚じゃないので、食べ慣れていないというのが大きな理由だと思います。僕自身、小さい頃にイワシを食べていた記憶がないですから。
でも、マイワシがすごく美味しい魚だというのはわかっていたので、何とかしたくて。それで考えたのが、マイワシの価値を高めようということでした。グラム当たりの価値を最大化するために1番いい方法として、自分の店でもよく使っていたアンチョビを作ってみようと思ったんです。

- 齊藤さん
- マイワシの価値が上がれば、漁師さんの収入が増えるじゃないですか。水産加工の方たちも、イカがとれなくなって塩辛作りができなくなってきていると聞いていたので、空いている樽を使ってアンチョビが作れたらいいんじゃないかなと思ったんですよね。同じ発酵食品なので。
そんなときに、シエスタハコダテで岡本さんと会ったんですよ。彼がフィッシャーマンズマルシェという企画でマイワシの販売をしていたのは知っていたので、これからアンチョビを作ろうと思ってるという話をしました。そしたら、岡本さんの目がギンって見開いたんですよ(笑)。
―それは、どういう反応だったんですか?
- 齊藤さん
- 岡本さんも漁師さんと一緒にマイワシを販売するなかで、アンチョビが答えなんじゃないかと思っていたみたいで。だから、僕がアンチョビって言葉を発したときにビックリしたらしいんですよ(笑)。そこからワーっと話が盛り上がって、ハコダテアンチョビの企画が立ち上がりました。

―実際のアンチョビ開発は、最初にイメージした通りに進んだのでしょうか?
- 齊藤さん
- いや、簡単にはいかなかったですね。いろんなレシピを調べたんですけど全部違うし、学術的な文献を探してみても日本語のものが見当たらなくて。発酵のメカニズムって本当にたくさんあって、使う菌の種類も様々なので、あれこれ試してみたんですけど最初はぜんぜんダメでした。
僕はアイディアで勝負するタイプのシェフなので、はっきりイメージができたものは大抵うまくいくんですけど、アンチョビは苦労しました。でも、楽しかったですね。仲間がいたので。同じ方向を向いて、後押ししてくれる人がいると、やっぱり頑張れるんですよ。ひとりだったら途中でやめていたかもしれません(笑)。
―それくらい大変な開発だったんですね。
- 齊藤さん
- 普通のアンチョビって、カタクチイワシを使うんですよ。だからまず、マイワシでアンチョビを作るという前例がなくて。だけど、岡本さんとはずっと「このプロジェクトはきっと地域産業を盛り上げることに繋がるから、絶対に壁を乗り越えよう」って話をしていました。

完成した函館アンチョビ。原料はマイワシと塩、こめ油のみで作られている。
―それはきっと普段されている料理とはまったく違う作業ですよね。科学者のようなアプローチというか。
- 齊藤さん
-
まさに、そんな感じでしたね。「俺って何屋だっけ?」みたいな(笑)。ようやく納得のいくものができたのは、試作を開始してから約4ヶ月後のことでした。
一番難しかったのは熟成の部分でした。熟成期間は2ヶ月くらいで十分だと思っていたんですけど、それだとタンパク質が変性されず、味も匂いも塩漬けの魚だったんですよ。要するに発酵しきれなかったんです。そこから温度を変えてみたり、魚をおろして漬けるか、頭のまま漬けるかなどの試行錯誤を続けました。ネットで参考事例を調べて、英語を日本に訳したりしながら。

―今はインターネットで世界中の情報を調べることができますが、はこだてわいんさんがスタートした50年前は状況がずいぶん違いますよね。ゼロからのワイン作りには、相当な苦労があったのではないでしょうか?
- 渡辺さん
- そうですね。先人から聞いた話ですが、当時は痩せた土地のほうがブドウ作りに適していると言われていたそうです。痩せた土地と言えば火山灰土ということで、駒ヶ岳山麓でブドウを育て始めてみたものの、満足のいく収穫はできなかったみたいですね。管理が悪かったのかもしれませんが。
それで結局は余市の果樹専門家に協力してもらって、ワインを作ることになりました。土地のことひとつとっても、伝え聞くものと、現実には大きな隔たりがあったので、最初は本当に試行錯誤の連続だったそうです。

―最初はブドウを作るところからスタートしたんですね。
- 渡辺さん
- 当時の日本では、フランス系のワイン作りが多かったんですよ。要するに畑も醸造も一緒にやらなければいけないという認識だったようです。他のお酒では、そういうことはないですよね。ビール会社は麦から植えないし、日本酒の酒蔵もお米から作っているわけではありません。だけど、ワイン事業だけは、畑も醸造も一緒にやるものだというイメージがあったんですよね。

販売所のワインセラーには1973年の創業時に作られたワインが展示されている。
―函館で上手くいかなかったブドウの栽培を、余市でやることになったのはなぜだったんですか?当時から余市はブドウの産地だったのでしょうか?
- 渡辺さん
- いえ、余市はリンゴ農家さんが多かったですね。だけど、だんだんとリンゴでは食べていけない農家さんが増えていました。そういう状況もあり、はこだてわいんに賛同してくれた7軒の農家さんが、リンゴの木を切ってブドウを作ってくださることになったんです。
―えぇ!リンゴからブドウに植え替えてくれたってことですか?
- 渡辺さん
- そうなんです。そうやって人生をかけてブドウを作ってくださった農家さんが7軒あって、今では「余市7人の侍」とも呼ばれているそうです。今も2軒の農家さんとお付き合いが続いています。はこだてわいんから離れた方も別のワイナリーと提携して、みなさん活躍されていますね。

40年ぶりに再会した自社農場(七飯町) 写真提供:はこだてわいん
―ブドウの栽培だけでなく、ワインの醸造についてもゼロからのスタートだったわけですよね。
- 渡辺さん
- そうですね。教えを乞う人もいなかったので、独学で試行錯誤を続けていたようです。
―すごいですね。独学でワイン作りを。それはハコダテアンチョビの開発と通じるところがありますね。
- 齊藤さん
- そうですね。発酵って菌の仕業なので、人間がこうだと思っても、どこかでテコ入れが必要なタイミングがくるんですよ。セオリー通りやったとしても、菌が予期せぬ動きをすることがあるので。それに対応するノウハウを持っているのが、日本酒であれば杜氏、ワインだったら醸造責任者ですよね。知識と経験がある人が舵を握って進めていくので、独学で作るのは大変だったと思います。
- 渡辺さん
- うまくいくと発酵、失敗すると腐敗。そういう世界なので、最初は失敗もあったんだろうなと思います。
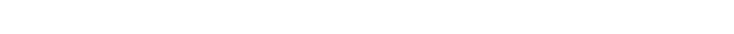
作り手としてのこだわりと、
お互いの商品に対する印象






